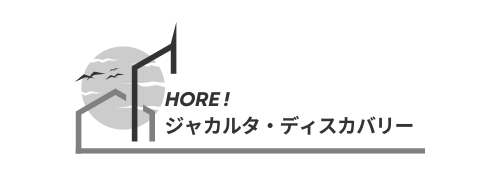こんにちは、ジャカルタで暮らす会社員のサントソです。
前回は青森県立美術館を紹介しましたが、青森と言えば「ねぶた祭」ですよね!ねぶたと言われる大型の灯籠を大人30人程で動かして街を練り歩くのです。ねぶたの近くではハネトと言われる踊り子が「ラッセーラ」と掛け声をかけながら飛び跳ねるように踊ります。「ラッセーラ」という掛け声は一説によると、ろうそくや菓子を「出せ出せ」とねだる文句のようです。今は蛍光灯でねぶたを照らしていますが、昔はろうそくで照らしていたため、そのように言われています。
そして青森県には、ねぶた祭を紹介する施設も有るのです!名前は「ねぶたの家 ワ・ラッセ」です。場所と外観はこちら。JR青森駅から徒歩1~2分くらいの場所にあり、施設の裏へ行くと海が広がっているので抜群のロケーションです!
 「ねぶたの家 ワ・ラッセ」の外観
「ねぶたの家 ワ・ラッセ」の外観この施設では、ねぶた祭りの歴史や作り方を紹介するのは勿論のこと、実際にねぶたに触れるコーナーも有ります。また、時間によっては囃子演奏・体験やハネト体験をすることもでき、30分ごとに大型スクリーンでねぶた運行の迫力のある様子が流され、来場者を楽しませてくれます。
そして、この施設のメインと言える場所が1階の「ねぶたホール」です!ここでは前年に賞を取った大型ねぶたが展示されています。通常、ねぶた祭が行われるのは8月2~7日にかけてですが、ここでは年中大きくて迫力のあるねぶたを見ることができます!実際に生のねぶたを見ると、パワフルで美しい!
 近くで見ると迫力があります。美しい!
近くで見ると迫力があります。美しい!このエリアでは通常見ることのできないねぶたの内部を見ることもできます。大枠は木でできているのですが、ワイヤーによって細かな表現ができているのですね。内部もなかなかの迫力が有るのですが、写真だと上手く伝わらないのが悔しいところです。
 ねぶたの中はこんな感じ。
ねぶたの中はこんな感じ。このエリアでもう一つ素晴らしい点が有ります。津軽弁で「もの知り、博学な人」を指す「覚様(おべさま)」という文字が後ろに書かれた半被を来た方がいるのですが、わからないことが有ればいろいろとその方に聞けるのです!めちゃめちゃ有難い!
 実際に置かれているねぶたと近くで解説してくれる覚様
実際に置かれているねぶたと近くで解説してくれる覚様以前、バリ・ヒンドゥーの宗教行事でねぶたに似たオゴオゴを紹介しましたが、オゴオゴは人間の本性の悪を意味しており、行事の最後に燃やされてしまうのです。しかし、ねぶたは特に悪いものを象徴していないので最後どうなるのだろうと疑問に思っていました。今回良い機会だったので覚様に思い切って聞いてみました。さて、回答はというと「1日の内に解体されてしまう」ようです。儚い!ねぶた祭りを本業にしている方はなかなかいらっしゃらないようで、資金は基本的にスポンサーから集め、多くはボランティアで成り立っているようです。その為、解体にもそんなに時間が割けないとのこと。華やかな祭りの裏にもいろいろと苦労があるようで勉強になりました。覚様、有難うございました!
バリのオゴオゴにしても青森のねぶたにしても、最後は無くなってしまう運命にありますが、このように無くなるまでの間に少しでも多くの人に見てもらう施設を作るのはすごくいいことですね!とても面白かったです。
次回もお楽しみに!Sampai jumpa!